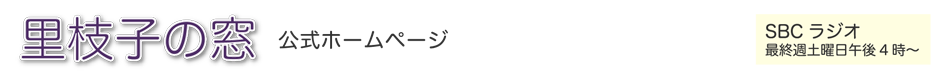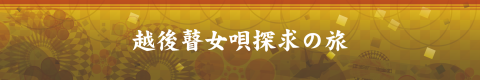広沢里枝子が取り組む瞽女唄(ごぜうた)の演奏活動をご紹介します。

イベント情報
![]() イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.6『瞽女唄の息吹』」
イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.6『瞽女唄の息吹』」
![]() イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.5『瞽女唄の息吹』」
イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.5『瞽女唄の息吹』」
![]() イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.4『瞽女唄の息吹』」
イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサートinこうのす・紫苑 vol.4『瞽女唄の息吹』」
![]() イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサート in 保養の家・武石」
イベント情報「広沢里枝子の越後瞽女唄コンサート in 保養の家・武石」
エッセイ
![]() エッセイ「越後瞽女唄探求の旅 一の段 - 広沢里枝子と瞽女唄との出会い -」
エッセイ「越後瞽女唄探求の旅 一の段 - 広沢里枝子と瞽女唄との出会い -」
その他
![]() 2022年7月6日からの信濃毎日新聞連載記事「広沢里枝子さんと越後瞽女唄」
2022年7月6日からの信濃毎日新聞連載記事「広沢里枝子さんと越後瞽女唄」
![]() 2019年の「みんなの皆野ノスタルジア - 私たちが伝えのこしたい郷土芸能 獅子舞曲・平曲・越後瞽女唄」(YouTube)
2019年の「みんなの皆野ノスタルジア - 私たちが伝えのこしたい郷土芸能 獅子舞曲・平曲・越後瞽女唄」(YouTube)
瞽女唄(ごぜうた)について 私は、2015年から、依頼をいただいたときに、少しずつ瞽女唄の演奏をしています。
私は、2015年から、依頼をいただいたときに、少しずつ瞽女唄の演奏をしています。
瞽女唄は、瞽女さんたちが、暮らしのために唄った唄です。瞽女さんというのは、家々を巡り歩いて、三味線伴奏で唄った盲目の女旅芸人のことです。
関東甲信越など、日本各地に見られた瞽女さんの姿は、今は失われてしまいました。ですが、瞽女唄には、400年近くの歴史があり、日本の庶民によって長年愛されてきた唄です。
私は、最後の瞽女と呼ばれた小林ハルさんが102才のときに、黒川村へラジオの取材に行き、1度だけハルさんの唄を聞きました。その感動と衝撃が、私が盲導犬とともに新潟に住む萱森直子先生のもとへお稽古に通う原動力になっています。萱森先生は、小林ハルさんや、杉本シズさんから直接瞽女唄を習い、瞽女唄の伝承活動に献身されている方です。
私の命は、両親や、無数の先祖達によって受け継がれました。それと同時に、障害や病をえながら生き抜いた無数の人々によって受け継がれたものだと感じています。
私にとって瞽女唄の探求は、命の水源をどんどん遡っていくことなのです。
(文・広沢里枝子)